離婚するときの慰謝料、本当にもらえるの?という疑問のお持ちの方へ
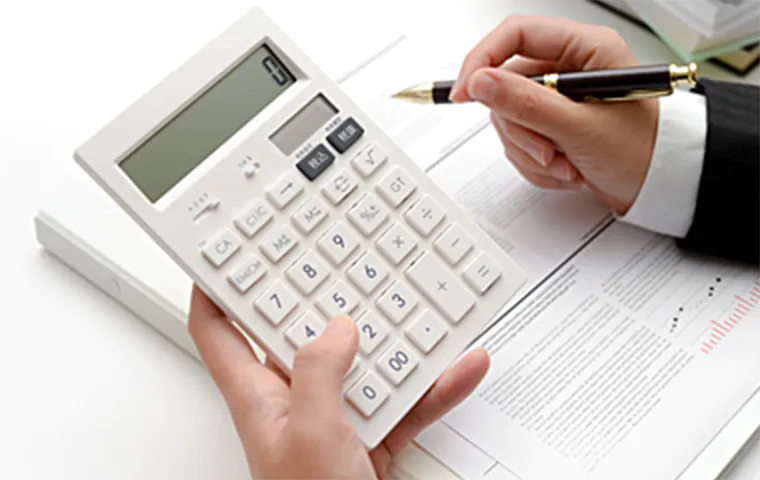
離婚すると芸能人がたくさんの慰謝料をもらったなどと報道がされることがあります。しかし、多くの場合には解決金であったり財産分与であったり、本当の法的な慰謝料とは「異なるもの」を「慰謝料」として説明してしまっている不正確な報道も多そうですね。慰謝料というのは精神的な損害を補てんするための「正義の法制度」です。そして、不法行為という「悪いこと」をした人が損害賠償を支払うという制度が基礎になっているものなのです。
よくあるご相談内容例
- 夫(妻)が浮気をしたので、離婚しないで相手から慰謝料をもらいたい
- モラハラで悩んでいます。モラハラで離婚して慰謝料もらえますか?
- 暴力を受けているので離婚したいのですが、慰謝料はいくらくらい?
Advantage | 離婚原因に関する東京ジェイ法律事務所の強み

Advantage.01
慰謝料をもらう手続きは多様、可能性を多角的に分析します
慰謝料がほしい、どうやったら払わせられるか?というご質問は多いのですが、方法はいろいろあります。方法ごとにメリットとデメリットがあります。協議で払ってもらえるのがもっとも早いですが、相手が無視したら終わりです。婚姻関係を続けながらの不貞の慰謝料請求はデメリットも多いです。単にがんがん請求しましょうというのは、依頼者にとって不利かもしれません。当事務所では多角的に状況を分析して手続きについてアドバイスします。
Advantage.02
慰謝料の証拠がどのようなものがあるか、丁寧に分析
慰謝料がほしい、という場合、障害になるのは証拠があるか、立証できるのか、という問題と、時効になっていないかということです。協議で払ってもらうにしても、こういう証拠があると開示しないと、相手もなかなか請求に応じません。しかし、依頼者によっては証拠がとても弱いということもあります。証拠の量とか質によって戦略も変わりますので、依頼者からの聞き取りによって証拠を丁寧に分析します。

- Promise.01 事情を丁寧に聞きます
- Promise.02 様々な方法のご説明
- Promise.03 慰謝料請求訴訟にも対応
- Promise.04 離婚事件との一挙解決も
- Promise.05 気持ちにあった解決
About | 離婚慰謝料はどういうときもらえるの? 相場はどのくらい?
1 離婚慰謝料とは何か?
法律的には、離婚慰謝料には二種類あるといわれています。
- 個別の行為に関するもの
例えば、暴力とか不貞(不倫・浮気)、悪意の遺棄などによって認められるものです。
そういう個別の悪い行為を理由に精神的苦痛に対して慰謝料が請求できるのです。 - 離婚そのものによる精神的苦痛の慰謝料
これは離婚という結果そのものでうける苦痛による慰謝料です。
そもそも慰謝料とは何なのでしょうか?
慰謝料は、精神的な苦しみに対してそれを補てんするために被害者がもらえる損害賠償なのです。
ですので、本来は苦しみが大きいならばそれだけ多く、もらえることになります。交通事故などで後遺症が残った被害者がもらえるものと同じです。
裁判所の判断では、上の①と②をはっきり区別して判決がでないことがほとんどです。
しかし、この慰謝料の内容についてしっかり書いてくれている判例もあるので、ご紹介してみますね。
<東京高裁:平成21年12月21日>
相手方の行為によって離婚を余儀なくされたということ「全体を一個の不法行為として」、そこから発生する精神的苦痛に対する損害賠償請求と扱われるのが普通だということを述べてから、「その場合、その間の個別の有責行為が独立して不法行為を構成することがあるかについては、当該有責行為が性質上独立して取上げるのを相当とするほど重大なものであるか、離婚慰謝料の支払いを認める前訴によって当該有責行為が評価し尽くされているかどうかによって決するのが相当である」とあります。
これは、離婚慰謝料というのは全体の行為をひとつとして判断してきめるのが普通で、それに加えて、暴力行為などを別に慰謝料請求の基礎にできるのか、追加で請求できるかということを検討しているのです。
追加で請求できる場合というのは、どういうときなのか?
これは、以下のようになります。
⇒その行為が重大なのか
⇒前の訴訟などで、すでにその損害が賠償されていないか
を見極めて決める。
2 離婚慰謝料の相場はいくら程度なのか?
離婚に至る経過というのは人によって千差万別ですから、相場と言いうのは難しいです。2011年に東京家庭裁判所で訴訟で認容された件数で言うと以下のようです。(東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情(第3版)判例タイムズ社より)
離婚慰謝料の金額:
100万円以下 28.2%
100万円より多くて200万円以下 26.6%
200万円より多くて300万円以下 24.8%
300万円より多くて400万円以下 7.2%
400万円より多くて500万円以下 8.1%
500万円より多い 5%
通常の判決では、300万円が上限であるという印象があります。
どういう場合に高額になるかというと、以下のような要素があります。
離婚慰謝料を要因決める要因
* 肉体的・精神的苦痛の大きさ
* 行為の有責性が高いか(より悪い行為かどうか)
* 婚姻期間が長いか
* 財産分与で経済的な補てんがされているか
* 有責ではない配偶者の資力があるか
* 未成年の子がいるか
たとえば、夫婦双方に問題の行動があっても、妻が夫の職場に押し掛けたり、夫を非難する電話をしたなどの行為が行き過ぎと判断された事例もあります(東京高裁 昭和58年9月8日)が、この判例では妻が100万円を支払うよう命じられています。
夫に不貞(不倫)があっても、夫婦関係の改善に妻も努力しなかったというようなことから、夫の慰謝料が低くなるような場合もあります。不貞を疑った妻に暴力をふるった夫の事案では、そういった妻の行為が考慮され、夫の慰謝料は低めの30万円と命じられています(東京高裁 昭和50年6月26日)。
このように、判例では夫婦の歴史をみて最終の判決をくだしますので、現実の事案によって20万円から500万円までの幅があるといえるでしょう。
適切に交渉する弁護士がついている事案では、判決よりも慰謝料が多い形で和解することも多いと思われます。それは、夫が払う婚姻費用が判決確定まで続くために、それを考慮した金額を交渉で勝ち取れるからです。
もっとも、判決での金額のほうが高いと見込める場合には、そういった和解がなかなか成立しませんし、当事者が事件を終わらせたいと思っているかにもよりますので、当事者は弁護士とよく話し合って和解の機会をうまくつかうのがよいでしょう。
3 離婚の原因と離婚慰謝料の関係
3-1 不貞(不倫)と離婚慰謝料
不貞(不倫)行為があった場合、不貞(不倫)をした方からされた方に慰謝料が命じられます。
高齢者の離婚で不貞(不倫)が理由の場合高額の慰謝料を認める傾向が判例にはあります。
特に、夫が不貞(不倫)相手と長期間同居している場合です。
例えば、東京高裁 昭和63年6月7日の判例は、慰謝料1000万円を夫に命じました。別居期間は17年、同居期間38年の事案です。
3-2 極端な浪費
極端な浪費があり、資産がある夫で他にも問題行動がある夫の場合、高額な慰謝料が命じられる傾向があります。
夫が年間500から600万円をバーなどで浪費し、夫の不貞(不倫)行為もあった事案では、夫に慰謝料を600万円が命じられているものがあります(神戸地裁 平成2年6月19日)。
妻に傷害を負わせて自宅に戻らず、危険を感じた妻が娘のアパートに身を寄せたという事案では妻へ500万円の慰謝料が認められました(仙台地裁 平成13年3月2日)。
しかし、500万円をこえる判例はあまり見られず、300万円程度の判決が多いように思われます。
また、お互いが相手の浮気を主張することもあり、それが立証できなくてもそういう疑いをもたれる行為があると、それが離婚原因にもなっている可能性があるため、慰謝料が減額される傾向もあるようです。
慰謝料についてきちんと主張するには、それが離婚の原因とどのように結びついているのかを見極める必要があります。
そのためには、代理人弁護士ときちんと法律的な主張の構成をつくって整理して主張することが大事です。やみくもにこういうことがあったという主張をすると「こういうことをするから、仲が悪くなったのだ!」と相手にむしろ使われてしまうこともあります。
夫や妻への慰謝料請求は不貞(不倫)の相手が特定できなくても認められますし、不貞(不倫)が立証できなくても遺棄したといえるような場合、遺棄したことで慰謝料を請求できることもあります。よって、放置するのではなく、不貞(不倫)で別居となった場合、早めに遺棄をされたことを弁護士に書面で主張し、「遺棄された被害者」であるという証拠を残すのが重要でしょう。
3-3 暴力
包丁で切りつけるような殺人罪を犯しうるような暴力であれば、慰謝料もかなり高額にあります。
もっとも、当初は穏便に済ませようと被害届を出さない場合が夫婦には多く、のちの訴訟で立証ができないということも多いです。高額な事案となっているものは、当時刑事事件になっており、暴行態様がきちんと立証できたものといえるでしょう。
横浜地裁は、些細なことで殴る蹴るの暴行をしていた夫に400万円の慰謝料の支払いを命じています(横浜地裁 平成9年4月14日)。
夫婦喧嘩で顔面骨折のけがをさせて入院が必要となったというケースでは、200万円が財産分与とは別に命じられています(神戸地裁 平成6年2月22日)。
3-4 夫婦の協力義務違反などの行為
一方が協力しないために夫婦が破綻したというような場合、協力しない方からの支払いが命じられます。
一方的で非妥協的態度、妻の人格を認めず劣ったものとして扱い、自分の母への親孝行をしないと思い込んでいた夫に対して、150万円が認められた事案(横浜地裁 平成3年10月31日)がありますが、こういった経緯は立証できることはあまり多くはないでしょう。
また、常識を逸した行動が夫婦の破綻を導いたような場合にも、慰謝料が認められます。これも立証は難しいでしょうが、浪費などは立証がカードなどで比較的しやすいといえます。
たとえば、年収600から700万円の家庭で、習いごとに年400万円を費やしたなどで、妻に対して200万円を夫に支払うように命じた、大阪地裁 平成6年10月28日の事案もあります。
3-5 セックス拒否
セックス(性交)の拒否については、なかなか調停などでは話しにくいことですが夫婦にとって大事なことです。
民法では婚姻した夫婦は他の人と性交渉をすると貞操義務違反になり、夫婦がお互いに合意に基づいて性交渉をすることが予定されているのですから・・・。
性交渉ができない夫婦の場合と離婚
よって、セックス拒否が病気などの正当な理由がなく、それが原因で婚姻が破綻した場合には、拒否された方に慰謝料が認められることになります。また、婚姻生活においては性関係が重要なので、婚姻に際しで性的不能を告知しないことは信義則上「違法」という評価を受けます。
京都地裁 昭和62年5月12日の判決は、以下のように、200万円の慰謝料を認めました。
この夫婦は、約三年半の間夫婦として同居していたのにもかかわらず、夫には性的興奮や性的衝動が生じていなかったと認定され、「婚姻が男女の精神的・肉体的結合であり、そこにおける性関係の重要性に鑑みれば、病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由に該る」としました。
その上で慰謝料については性交渉ができないことの告知については、「婚姻生活における性関係の重要性、さらには、性交不能は子供をもうけることができないという重要な結果に直結することに照らすと、婚姻に際して相手方に対し自己が性的不能であることを告知しないということは、信義則に照らし違法であり不法行為を構成する」として、この事案では200万円の慰謝料が認められました。
夫がポルノ雑誌に異常な関心を示して通常の性交渉がなくなった場合
こういうことはありえるとみなさん思われるかもしれませんが、ポルノ雑誌などが好きでリアルな夫婦のセックスがないような場合、それで夫婦関係が破綻すると離婚原因となりますし、慰謝料が認められることもあります。
夫婦の関係でなすべき性交渉が、夫がポルノ雑誌に異常な関心を示し始め、買いあさっては一人で部屋に閉じこもって自慰行為に耽り、原告との性交渉を拒否したことが認定され、その他の夫の問題行動もあったことから、夫に慰謝料500万円が命じられている事案があります(浦和地裁 昭和60年9月10日)。
妻が気持ち悪いといって拒否している場合
こういう場合、夫がかわいそうというか、それなら妻が結婚しなければよいと思いますよね・・・。
岡山地裁では、男性に触れられると気持ちが悪いと言いセックスを拒否していた妻と喧嘩が絶えず破綻したという事案では、精神的に妻が性交に耐えられないという医師の診断があったものの、妻から夫への慰謝料150万円の支払が命じられています(岡山地裁地津山支部 平成3年3月29日)。
一般的には妻がセックスがらみで慰謝料を命じられることは、不貞(不倫)以外には珍しいですが、夫の人生設計に関して重大な事実を先に伝えなかったのでこういうことになったのでしょうね。
性交渉に関心がない夫との短期間での離婚の場合
夫が性交に無関心のため、性的関係のないまま婚姻して1か月程度で別居した事案で、妻がいったん結婚退職していたために、再就職しても以前の3分の1以下の収入しかなく、これまでの貯金も結婚費用として450万円弱使っていたことなどが考慮されて、夫に500万円の慰謝料の支払を命じられている事案もあります(京都地裁 平成2年6月14日)。
4 扶養義務と慰謝料の関係
婚姻が破綻するに至る経過とか、離婚後の配偶者の経済的自立の可能性を総合的に考慮して、裁判所が慰謝料を認めることもあります。
しかし、これは稀です。
現在の訴訟実務では、夫婦の共同財産を財産分与として認める際に、扶養についての側面を考慮することがあります。
財産分与がないような場合で、夫婦の経済的自立の観点から慰謝料を認めることはほとんど、ないでしょう。
現在の判例の立場では、夫婦の経済力がかなり異なっても、通常の慰謝料に加えてその夫婦の経済的な差異を理由に、慰謝料を追加して払わせるという判決はでないと考えてよいように思えます。
もっとも、離婚に至る経緯の中で、夫が婚姻費用を支払っていないなどの特別の事情があり、夫が有責であれば総合判断として、離婚が認められないことがありえると思われます。
5 慰謝料が認められないのはどういう場合か?
5-1 相手方の行為に違法性がないとき
慰謝料は、その行為に違法性がないと判断されれば、請求できません。
たとえば、違法性がないとされた事案は以下のようなものです。
1) これは、妻の情緒が不安定で衝動的な行動を繰り返す妻への夫からの慰謝料請求の事案ですが、妻の精神病質によるものであったので、倫理上道義上の非難の対象とはならないとしました(東京高裁 昭和51年8月23日)。
2) 夫の奇異な行為、性交中に離婚をしたいと言い出したり、長男の入院先の病室へ離婚届用紙を持参するなどの行為については、「不法行為を構成する違法性はない」としています(名古屋高裁 平成18年5月31日)。
夫婦の間の行為はお互いが誇張して攻め立てることが離婚事件では多いです。
離婚訴訟では、互いが何でも違法行為だと主張することも多いですが、裁判所は破綻の原因となっている行為でも、それが、不法行為を構成するかどうかを判断しますので、慰謝料は容易に認められないことに、留意しましょうね。
5-2 二人ともに責任があると判断されたとき
たとえば、夫は暴力をふるい、妻が不貞(不倫)行為をした場合、双方の行為で夫婦が破綻していますので、双方からの慰謝料は否定されています(東京地裁 昭和55年6月27日)。
妻の過剰な宗教活動で破綻した例で妻の有責性が認められているものの、夫にも暴力を用いたという帰責性が認められた事案では、夫からの慰謝料請求は否定されています(仙台地裁 昭和54年9月26日)。
夫婦が中年またはそれ以上で婚姻期間が長い場合、長年にわたって、事情が複雑で多様な影響している事案では、総体的には双方にそれぞれの帰責があるのが公平な評価であると考えられ、破綻原因が専ら一方によるものではないとされる傾向があるでしょう。
5-3 破綻と行為の間に因果関係が認められない場合
不法行為によって夫婦が破綻して離婚にいたるという因果関係が認められないと、慰謝料請求は認められません。
たとえば、不貞(不倫)行為より前に夫婦が破綻していたとして、妻からの慰謝料請求を否定した事案があります(東京地裁 昭和63年10月12日)。
ですから、不貞(不倫)行為が別居してからであることが立証できれば、このように不貞行為をした者も慰謝料請求を回避できます。
そういう意味で、いつから別居していたのか、その証拠があるかは重要です。
5-4 違法行為はあったが、損害賠償がすでになされて補填がされていた場合
不貞(不倫)行為の場合、民法では、配偶者と相手方の共同不法行為ということになりますので、慰謝料の支払い義務は二人が負っています。民法ではそれを不真正連帯債務といいます。
よって、すでに不貞(不倫)相手から慰謝料を得た場合、離婚慰謝料についてはその限度では否定されてしまいます(東京地裁 昭和61年12月22日)。
すでに損害が補填されているからです。
よって、不貞(不倫)の相手に対して提訴して慰謝料請求をするよりも、配偶者への離婚請求の中で慰謝料請求をした方が、効率がよいことがよくありますので、慰謝料請求をする場合、効率性も考えたほうがよいでしょう。
離婚慰謝料は、 離婚を強いられた者の精神的苦痛を補てんするとともに、その責任の所在を明らかにすることで、婚姻の倫理上の義務を明確にしたり、財産分与の不十分さを補ったり、離婚後の生活を保障する機能がある場合もあります。
日本では、まだ完全な破綻主義を採用せず、有責主義が制度的に残っていますので、夫婦が破綻したときに主たる原因をつくった相手方は慰謝料を払うことになる傾向があります。しかし、時代と共に慰謝料金額は低減する傾向があり、被った苦痛の程度に十分に応じた額にはなっていないという意見が多いです。
また、一方または双方が互いに慰謝料請求をして、離婚訴訟が長引き、相手を非難し続けることが、不安感やストレスの原因となってしまうこともあります。
特に、夫婦であったものがお互いを人格攻撃することによる、子への悪影響も無視できません。そのような非難の応酬をしながら、面会交流を実現するのも非常に難しいものです。
実務家弁護士はそういった側面に考慮して、離婚訴訟における慰謝料請求は当時者にとっても利益にならないことが多いことから、調停や和解離婚で解決金という名称で支払いを実現して、早期に解決する策を用いることも多いです。
わが国では、海外で認められているような「離婚後の扶養義務」を一方に課すことができず、養育費は子供のための費用としてしか認められていませんが、子を育てる親の生活レベルの維持という点では、妻や夫への扶養も認められるべきなのかもしれません。
6 不貞(不倫)行為の相手方に対する慰謝料請求が認められるのは、どういうときか?
6-1 判例動向
浮気を知った人は、配偶者ではなくその相手に対して慰謝料請求ができますが、必ず請求が認容されるわけではありません。
一般的に日本で慰謝料請求が認められる理由は、
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである」と昭和54年の最高裁判例が言っています。
もっとも、後述する平成31年の最高裁判例から、不貞(不倫)行為のみならず、夫婦の権利を侵害する故意の立証責任が、明確に原告に課されるようになっています。
平成8年3月26日の最高裁決定(後で詳しく説明します。)では、配偶者の一方と肉体関係を持った第三者は「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは特段の事情がない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」と明言して、「婚姻共同生活の平和の維持という権利ないし法的保護に値する利益を侵害する」ことが、慰謝料請求が認められる根拠だと、示しています。
そうすると夫婦が「破綻」しているかの点が重要になりますが、通常は夫婦の「別居」によって破綻を認定する傾向があります。
よって、通常は別居後に不貞(不倫)の関係が発生しても、第三者の不法行為資任は発生しません。
不貞(不倫)行為によって夫婦が離婚や別居にまで至っていなくても、他方配偶者に多大な精神的苦痛を与え、夫婦関係に深刻な不和をもたらすとして、不法行為を認めることが多いものの、認容額が少なくなります。
通常の認容額は、上限が300万円であり、100万円以下の場合も相当あるようです。
1996年の有名な最高裁の判例では、不貞(不倫)行為の相手方の不法行為責任が否定されていますので、紹介しますね。
<最高裁の事案>
夫婦は1967年に婚姻して子が二人いました。夫婦関係は性格の相違や金銭感覚の相違などが理由となり、次第に悪くなっていきました。
1984年に、夫がABC 株式会社の代表取締役に就任し、その会社のために自宅の土地建物に抵当権を設定したことで、妻はこれを非難して財産分与をせよと要求しました。また、夫に包丁をちらつかせて脅すなどしました。
1986年、夫は、別居したいと思って離婚調停を申し立てたが、妻は夫に交際中の女性がいると主張していました。
1987年に、夫は病気のため入院し、手術後退院したのですが、入院中に当該会社名義のマンションを購入して、自宅を出て別居を開始してそこに住みました。
その直前の4月にある女性と知り合い、当該女性は離婚することになっていると夫から聞いてまた、別居していると説明を受けたので、その言葉を信じてく交際し、性関係を持ち、10月頃からマンションで夫と同棲を始めて子をもうけました。
この場合の妻から女性への慰謝料請求は認められませんでしたが、その際、最高裁は以下のように言ったのです。
配偶者と第三者が肉体関係を持った場合、その夫婦の婚姻関係がその当時既に破綻していたとき、特段の事情のない限り、その第三者は不法行為買任を負わない。なぜなら、肉体関係を持つことが不法行為になる場合とは、夫婦の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができる場合であり、婚姻関係が既に破綻していた場合、原則としてそのような権利又は法的保護に値する利益はないからである、というのです。
もちろん、実際の事案では、交際が始まったことと、夫婦の破綻とか別居がどのような関係にあるのかは、判断が難しく、別居前に交際が始まっている場合、慰謝料請求が認められることも多いといえます。
このように慰謝料請求が認められるかは、証拠があるかにかなり依存するので、請求をする場合には慎重な判断が必要でしょう。(最高裁 平成8年3月26日決定参照)
6-2 慰謝料が認められるときの要因は? 金額はどのくらいか?
慰謝料額は、違法性の程度や損害の程度で決まります。
*不貞(不倫)相手方と配偶者の年齢差、関係開始の主導権を誰が持っていたのか
*相手方の年齢や資力
*夫婦関係が不貞(不倫)行為により破綻に至った程度
*相手方と配偶者の関係が継続しているのか
*不貞(不倫)を行った配偶者自身の責任は宥恕されたのか
*請求する配偶者が未成熟子を監護しているのか
*その配偶者にも夫婦間の不和について落ち度があったか
というようなさまざまな事情が考慮されます。
傾向としては、払う方が男性である場合の方が、女性である場合よりも慰謝料額が高い傾向があるといえるようです。
これは男性の方が一般に資力があり、相手方が女性の場合非婚で子をもうけて生活に困窮している場合が多い、という事情によるようです。
慰謝料を認めた判例の動向と金額
1) 夫と女性との交際が20年程度あり、その間、夫は女性と性的関係があることを妻に話したり妻とこの女性を比べる話をしていたという事案では、ついに夫がその女性と同棲を始めたことから、女性に慰謝料300万円の支払いを命じた事案があります(大阪地裁 平成11年3月31日)。
2) 不貞(不倫)関係が夫が主導していたことから、女性への慰謝料は150万円のみ認めた事案もあります(横浜地裁 昭和61年12月25日)。
3) 夫が相手女性の上司であり、夫が主導的役割を果たしていること、妻は夫に何らの請求をせず許していることから、提起の目的は不倫関係を解消させることにあり、解消ができたということから50万円のみが認められている事案もあります(東京地裁 平成4年12月10日)。
不貞(不倫)にもかかわらず、夫と同居して夫婦関係を維持しようという妻が女性に慰謝料を請求する場合には、請求が認められない場合もありえ、認められても少額になるので、提訴は慎重になすべきでしょう。
4) 夫のいる女性と性的関係をもち、執拗にこの女性の家庭に電話をかけたり庭先で女性の名を呼ぶなどの行為や名誉棄損の行為をして、女性の夫婦関係を悪化させようとした男性の事案では、最終的に妻がこの男性と同居していたこともあり、500万円という高額の慰謝料を認めました(浦和地裁 昭和60年12月25日)。
5) 経営者の妻が会社従業員と性的関係をもった事案では、裁判所は「合意による貞操侵害の類型では自己の地位や相手方の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて相手方の意思決定を拘束したような場合でない限り、不貞(不倫)や婚姻破綻についての主たる責任は配偶者にあり、相手方の責任は副次的なものである」としています(東京高裁 昭和60年11月20日)。賠償額は200万円でした。
6) 10年以上夫と性的関係のない妻が、男性と知り合って4年後性的関係をもって、夫が止めたのに男性と同棲したという事案では、夫から男性に対する100万円の慰謝料請求が認められました(東京地裁 平成10年7月31日)。
7) 妻が経営する会社の従業員と不貞(不倫)した事案で、男性に対して200万円の支払いを命じています(東京地裁 平成29年10月18日)。
この事案では、原告の妻と男性の不貞(不倫)関係は5年以上の長期間であって、その時点で原告と妻の婚姻関係が破綻していたと認めることはできないとして、不貞(不倫)の発覚によって関係は終わったものの婚姻はすで10年以上と長く、夫はその間に懸命に仕事と家庭を両立させようとしてきたこと、今後離婚により長女と別居して面会交流をするという結果になったこと、が考慮されています。
6-3 慰謝料が認められない場合はどんな事案か?
慰謝料が認められなかった判例の動向
1) 破綻後の不貞(不倫)という認定の場合には、慰謝料は認められません。
たとえば、夫婦間で子どもの結婚後には離婚するという話合いがなされており、夫の単身赴任を機会に別居が始まった後、夫が他の女性と仮祝言をして同居した事案では、家庭生活の平和を違法に侵害していないとされています(東京高裁 昭和60年10月17日)。
2) 不貞(不倫)があっても円満な夫婦関係が維持されていた場合にも、損害が認められません。
たとえば、妻が夫を許して、夫と相手方女性の貢任は等しく、 相手方女性から夫に対する貞操侵害による慰謝料請求が棄却された等の事情を加味して「信義則・公平の観念に照らし」請求を認容しなかったものがあります(山形地裁 昭和45年1月29日)。
3) 夫の行為が第三者に対する性交強要である場合にも、相手には帰責性がなく慰謝料請求ができません(横浜地裁 平成元年8月30日)。
4) 権利の濫用にあたる場合も、請求は棄却されます。
夫婦の仲が冷めており離婚するつもりであると話したことから、不貞(不倫)が始まっていること、不貞(不倫)を知った妻が慰謝料の要求をするにとどまらず、夫の女性に対する暴力を利用して金員を要求したことなどの事情があり、信義則に反し、 権利の濫用として 許されないとしたものもあります(最高裁 平成8年6月18日)。
5) 婚姻していたと確認しなかったことに責任がない場合も、請求は認められません。
東京地裁 平成29年10月12日の判決では、原告の妻の不貞(不倫)行為の相手方である19歳であった被告男性に対し不法行為に基づき慰謝料等の支払を求めていますが、クラブで知り会って交際期間が8か月程度であったことや単なるセックスフレンドのような関係であったこと、妻は他にも交際相手もいたこと、被告の年齢・社会経験等から、未婚であるかを調査すべき義務があったということできないので、不法行為責任を認めることはできないとしています。
6) また、それだけではなく不貞(不倫)相手のほうで、夫婦を離婚させるというような意図があるなど特別事情が必要であることを、平成31年の最高裁が明言しており、慰謝料請求の立証責任が重いことが確認されました。
最高裁 平成31年2月19日決定は、「不貞相手である第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がない限り,当該第三者に対し,離婚慰謝料を請求することはできない」との判断を示しています。
不貞(不倫)相手に対して離婚慰謝料を請求するためには、特段の事情を立証することを要するわけなので、立証する責任として単なる不貞(不倫)ではなく「夫婦を離婚させる」などの意図が必要というわけで、請求者の立証責任は重くなったと、いえます。
7) 慰謝料支払の合意が無効である場合も請求ができません。
妻の不貞行為により、夫と妻は協議離婚し、夫が不貞相手に慰謝料3000万円を要求して家に押しかけて深夜まで長時間怒鳴り暴行をしたうえで、河川敷に連れ出して殴打したり「おまえを殺そうと思って、包丁を持って来た」など脅したという事案でした。
判決は「原告の意思表示は被告の強迫によって形成された瑕疵ある意思表示」と判断し取消しを認めて合意を無効としました(千葉地裁佐倉支部 平成22年7月28日)。
6-4 不貞(不倫)相手への慰謝料請求は消滅時効にかかるのか?
不貞(不倫)の慰謝料請求も不法行為に基づく請求権ですので、時効によって消滅します。
最高裁は、1966年頃夫の不貞が始まり、妻から1987年に慰謝料請求の提訴がされた事案では、21年間不貞が続いていたのですが、「一方の配偶者が右の同棲関係を知った時から,慰謝料請求権の消滅時効が進行する」としました(最高裁 平成6年1月20日)。
これは、不法行為は継続的になされているので、その不法行為の消滅時効に関する判例の考え方に従ったものです。
配偶者が不貞行為を知った時から、それまでの期間の分の慰謝料請求権の消滅時効が進行します。
破綻後の性関係については不法行為が成立しないので、別居の際に不貞(不倫)を知っており別居(破綻)から3年が過ぎている場合、時効で請求ができなくなることになります。
東京高裁 平成17年6月22日判決は、別居から1年2カ月経過した時点で破綻を認定して、慰謝料請求権がすでに時効消滅していると判断しています。
もっとも、別の高裁の事案では、20年近く同棲している女性に対する妻からの慰謝料請求を認めています。これは、女性の行為が破たんさせたのでなく、離婚させたとし、離婚が成立した時に初めて不法行為を知って損害の発生を確実に知ったという構成をして、200万円の慰謝料を認めています(東京高裁 平成10年12月21日)。
この事案は、遺棄された妻が既成事実を積み重ねられていたことから、妻の被害感情を満足させようとした解釈のようですが、時効との関係では理論的にすっきりしません。判例は事案ごとの妥当な解決を裁判官が導こうとするので、理論的には?ということもありますが、まさにこれはそういう高裁判例に見えます。
7 配偶者や不貞相手(不倫相手)に慰謝料請求をするのにベストな方法は?
7-1 離婚において慰謝料をもらうには、どんな方法があるのか?
実は、離婚におけるまたは不貞(不倫)行為に関する慰謝料の請求方法には、かなりのバラエティがあります。
列挙すると、以下が方法として考えられます。ずいぶんいろいろあるなあと、思われるかと思います。
- 協議をして払ってもらう方法
- 民事訴訟で提訴する方法
- 民事調停を使う方法
- 家事調停(離婚調停)を使う方法
- 離婚訴訟で請求する方法
離婚をする場合とそうでない場合で、実は、かなり請求できる額も、方法も異なるものなのです。
ですので、分けて考えてみましょう。
7-2 配偶者と離婚する場合
1) 不倫相手と配偶者双方に請求する場合
すでに上記でご説明していますが、不倫(不貞)は共同不法行為。
つまり交通事故で言うと、あなたの車に夫(妻)の車が突っ込んできて、その後ろには先に相手女性(男性)が突っ込んでいたという、玉突き事故のような状態なんですよね。
たとえば慰謝料金額300万円であれば、二人にまとめて300万円請求できますが一人から300万円を払ってもらったらもう一人には請求できません。ですので、どちらに先に請求するか、そうではなくて二人に同時に請求するのか、離婚協議・離婚調停において配偶者にまとめて払ってもらえばよいとするのか、という選択が必要になります。
金額としては、配偶者に請求するほうが大きくなりますので、効率を考えると配偶者だけということになりそうですが、離婚裁判(離婚訴訟)では不倫相手も相手にしてひとつの訴訟が認められていますので、その選択もありえます。
手続きを早く終わらせて離婚したいのであれば、配偶者にきちんと調停で払わせて謝罪もしてもらうというのが、一般的にはおすすめです。
しかし、そこは感情面もあって、「夫だけではなく相手に請求したい」というお気持ちがある場合には、個別にご相談して離婚調停・協議をしつつ、相手に対して提訴というような方法もありますので、ご説明して進めていきます。
要注意なのは相手に300万円の請求が認められても、相手はあなたの夫(妻)に求償ができてしまうという問題です(そんなのは自分には関係がない・・・というのであればよろしいかと思いますが・・・)。
2) 配偶者だけに請求する場合
上記の通り、慰謝料請求できる金額は配偶者への請求だけで「上限の金額」になりますので、これがすっきりします。
離婚原因を作ったのはあくまでも一義的には配偶者であるという考えが、現在の訴訟実務では強いので不貞相手への請求額は、より少なくなりがちですし、相手に対して請求すると相手は既婚であることを知っていたのか、相手はどういう態様で交際を始めたのか、夫婦の離婚を望んでいたのか、というようなことの立証が必要となり、「相手への請求が認められるか」という点では「敗訴する可能性」もでてきますし、訴訟も長引き費用もよりかかってしまいます。(一部でも敗訴なんて・・・不倫されてまで嫌ではないですか?)
ただでさえ、ストレスが多いのに部分的にも敗訴するのは無駄なストレスを増やすだけ。
そうすると、不倫の被害者にとっては、配偶者だけに請求するのが「王道」なのではないか・・・と思われます。
配偶者との離婚の話し合い・訴訟でまとめて請求ができますので、離婚原因を主張する中で主張すればよく、手続的にもシンプルです。
7-3 配偶者とは離婚しない場合
1) 不貞(不倫)相手に、協議で慰謝料を請求する場合
自分で請求する方もいるようですが、通常は弁護士が内容証明を出して請求します。
職場にわかるような形で通知を出すのは、弁護士倫理に反するのでできません。司法書士・行政書士がこのような通知を出すことは違法です。
ご自分で協議して念書などにサインをさせる方法は、弁護士費用が掛からないのがメリットですが、そもそも相手が無視することが多く、また、後で無効・取消の主張をされやすい、それから現実に支払いがされないことが多いという問題があります。
弁護士が請求した場合、相手にも弁護士がつくことが通常であり、弁護士の間の協議となります。そうなると、訴訟での相場に近い金額よりも高めで解決することが多いように思われます。それは、相手が、訴訟になって尋問までされることを(弁護士費用も追加となるので)嫌う、という背景事情があるからではないでしょうか。
さらに、弁護士がついていることから、いつでも訴訟が提起されることがわかり、相手が真剣に問題の解決をしようとしますので解決も早いです。なお、この訴訟は地方裁判所の通常民事訴訟になるため、名前が出ますし、本人尋問は公開法廷で行われます。
もっとも、上記で説明したように、夫と同居しているような(破綻していない)場合、訴訟では不貞(不倫)相手が、最高裁判例により婚姻関係を破綻させる意識がなければ慰謝料請求ができない傾向、認められても低額の可能性がありますので、配偶者との離婚を考える可能性があるのであれば、配偶者への請求に絞った方が、弁護士費用も押さえられます。当事務所では、離婚調停の際に配偶者を説得して、不貞(不倫)相手にも謝罪をしてもらい、感情的な問題を解決させつつ、訴訟における尋問のストレスを回避するというような解決方法なども、工夫しています。
2) 離婚はしないが、配偶者に慰謝料を払わせる場合
感情的にはそういうことをしたいという方はおられますが、同居して夫婦の協力義務もある中で請求する、提訴するというのは、今後の家族関係に大きく傷をつけるものですので、お勧めできません。やはり、不倫を許せるのか、許して夫婦関係を維持していけるのか、という点で、根本的な夫婦関係の再構築ができるかを検討するのが、人間として健全であるように思われます。
マリッジカウンセルなどもありますし、まずはお金ではなくて人間の関係として見直してみてはどうでしょう?
もっとも、話し合いをしてどうしても200万円をもらう約束をしたいというような場合もありましょうから、個別にご相談をうければ当事務所では配偶者間での取り決めの合意書などは作成しております。



